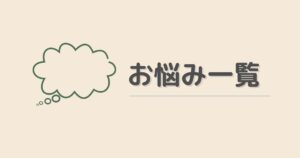3歳過ぎて言葉が出ていない…それでもトイトレは始められる?
3歳で言葉も出ていませんが、トイトレ(トイレトレーニング)はいつ頃から…
いえ、言葉が出ていなくても大丈夫です
この10年間、何度このやりとりを繰り返してきたことでしょう。もはや“教育相談あるある”の殿堂入りです。
トイレトレーニングについて、ネットや子育て本には誤った記述がかなり多いので、まずそこからお伝えしていきます。
①言葉が出ていなくてもトイレトレーニングは可能?
できます。言葉が出ていなくてもトイレトレーニングを始められます。
「まだしゃべれないから…」と始めるのをためらう保護者の方は本当に多いのですが、
私の教育相談では、むしろ言葉が出ていなくてもオムツ外しを始めるケースがほとんどです。
“しゃべれること”は、トレーニングに必要なスキルではありません。
②尿意のサインがなくても大丈夫?
意思表示がなくても、トレーニングは始められます。
尿意を言葉で教えてくれるかどうか──そこにこだわる必要はありません。
「あってもなくてもOK」。気楽に構えるくらいで大丈夫です。
たとえば「おしっこ!」と訴えがあっても、それが本当に尿意なのかどうかは分かりません。
でも練習を重ねていくうちに、訴えと排泄はだんだん一致していくんです。
だから、最初はズレてて当然。勘違いだって全然OKです。
実際、サインを待っているうちに半年、1年と時間だけが過ぎてしまうケースもあります。
これは、子どもの発達の面でも(そしておむつ代的にも)、ちょっともったいないことです。
そもそも、トイレに行きたいと伝えること自体が、大切なトレーニングの一環です。
最初からできなくて当たり前。
伝え方だって、言葉以外の方法も色々あるんです。その子にあった方法を作っていきましょう。
③知的な遅れ・言葉の理解が難しい子へのトイトレは?
それでも、トイレトレーニングは可能です。
トイレトレーニングは、実体験を通じて子どもに教えるものです。必ずしも言葉で説明して教えるものではありません。
たとえば、知的な遅れがあるお子さんに
「手を洗う」「スプーンで食べる」などの日常動作を教えるとき、
私たちは言葉だけで説明しませんよね?
- 実際に手を取って一緒にやってみる
- 環境を整えて、自然と行動が起きやすくする
- 「成功」を繰り返して覚えてもらう
トイレトレーニングも同じです。
「教える=言葉で伝えること」という思い込みを、一度手放してみましょう。
必要な行動を、小さく分けて、順番に教えていく。
そうすれば、どんなお子さんでも、トイレに向けて進んでいけます。
④トイレを激しく嫌がる子、どうすればいい?
大丈夫です。トイレは、ちゃんと「好きな場所」になります。
なぜなら、嫌がっていた場所を“安心できる場所”に変えていく方法があるからです。
「トイレに連れていこうとすると、毎回大泣き」
「トイレという言葉だけで逃げる」
そんな状態でも、子どもは自分からトイレに向かえるようになります。
ただし、ここで1つだけ大切な視点があります。
「これはトイレの問題だけじゃないかもしれない」という心構えをもってみてください。
- 声かけや指示への強い拒否
- 大人のペースに合わせることへの慣れのなさ
- 小さなきっかけでかんしゃくが出やすい状態
こうした“行動の土台”に課題がある状態では、トイレも難しく感じてしまうのは自然なことです。
目の前の課題には、実は背景がある。
それを一緒に見つけて、親子の成長を支えていくこと──それこそが、本当に意味のある支援です。
「トイレトレーニングの進め方」──“教科書通り”で本当にうまくいく理由
実は、トイレトレーニングに関しては、すでに非常に実用的な一冊が出版されています。
この10年間、私が教育相談でトイレトレーニングをサポートしてきたなかで、
この本の内容に沿って進めて、うまくいかなかったケースは一度もありません。
(もちろん「オムツのままで構いません」とご家庭が判断された場合は別ですが)
ご家庭ごとの事情に合わせてアレンジすることはありますが、
基本的な進め方は、この本の第3章に書かれたやり方をベースにしています。
私自身が信頼して使っている方法だからこそ、
「どこから始めたらいいかわからない」と感じている方には、
“道しるべ”としておすすめしたい一冊です。
支援現場で実践されているステップと工夫
私がご家庭にうかがってトレーニングを始めるとき、まずお願いするのは以下の2つ:
- 本を購入し、相談日までに目を通しておいていただくこと
- 記録の取り方など、細かい実践のコツをアドバイスすること
必要な準備や道具もすべてこの本に書かれているため、
親御さんが「やるべきこと」を見通せる状態でスタートできます。
当日は、朝のトイレタイムから立ち会い、誘導の仕方・記録・注意点を一緒に確認します。
そして準備が整ったら、「じゃあ一緒にやってみましょう」と声をかける──それだけです。
初めての排泄成功が訪れたときの空気は、毎回本当に嬉しいものです。
あとは親御さんにバトンを渡し、メールで報告を受けながら必要に応じてアドバイスします。
この本に書かれている方法は、再現性が高く、すぐに実行できる内容です。
大げさではなく、「これがあってよかった」と思える一冊になるかもしれません。
支援者・専門職の落とし穴──本当にトイレ支援の経験ありますか?
この記事を書いたきっかけは、あるご家庭の相談でした。
4歳をとうに過ぎているのに、トイレトレーニングが進まず、1年以上悩んでいた親御さん。
何人もの専門職に相談したそうですが、返ってくるのはいつもこんな言葉でした。
「言葉が出てからがいいですよ」
「本人の意思表示を待ちましょう」
「自閉症の特性なので…」
結局、状況は変わらないまま。
そんなとき、この本がきっかけで、1週間もせずトイレが成功。
親御さんから私に届いた言葉が、今も忘れられません。
実は、専門職の方、トイレの支援やったことがなかったみたいで…。
こうした話は、実は珍しくありません。
「知らないことを知らない」と認める強さは、専門職にとって大切だと思います。
そして、知らなければ学べばいい。
まずはこの分野の信頼できる教科書を、ぜひ一度手に取ってください。
もうすぐ小学生、でもまだオムツ…
「4月に小学校入学なんですが、まだオムツが…」
この相談は、毎年のように届きます。
でもこれは、ただ「トイレトレーニングが遅れた」だけの話ではありません。
よく見ていくと、家庭・支援者・そして社会のあいだに、小さなズレがいくつもある。
そしてそのズレがどんどん大きくなり、気づいたときには“どうにもならない状態”になっていた──
そんなケースも、実際にあるのです。
次回は、「就学直前、まだオムツ」の本当の背景と、支援が機能しなくなる構造を、
一つひとつ解きほぐしていきます。
後編の記事はこちら。


トイレトレーニング以外にも、当相談室は、様々な相談をお受けしています。
こちらのページが参考になります。
当相談室は、千葉県・東京都エリアを中心に、出張カウンセリングを行っています。
お子さんの発達や行動に関する悩みを、専門家が直接ご家庭にうかがって支援します。
お問い合わせはこちらから。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。