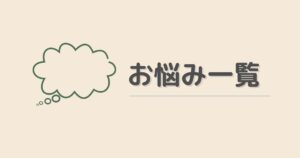駐車場で突然走り出す、ほんの一瞬で姿が見えなくなる──
3歳前後のお子さんを育てる親にとって、それは心臓が止まりそうな瞬間です。
今回の記事では、「大人のペース」という視点から、
外を安全に歩くための対応法と、家庭でできる練習ステップを具体的に紹介します。
3歳児が急に走り出すのはなぜ?──支援の前にお伝えすること
3歳の息子が、すぐに走り出してしまうんです。危ないと何度伝えても、まったく聞いてくれません…
これは大変です。もう最優先でやりましょう
道路や駐車場などで突然走るといった習慣がある。
こんなとき、たとえ言葉の練習を後回しにしてでも、真っ先に支援に取り組みます。
さて、親御さんもこの状況を何とかしたいと強く感じています。
まず何から始めれば良いでしょうか?
ここでお伝えするのは──
言い聞かせる、何度も注意する、といった対応は、もう無意味と割り切ってください。
なぜなら、相手は子どもです。
一度「うん」と返事をしても、3秒後には、また走り出します(そういう生き物なんです!)。
このようなケースで大切なのは、「成長すれば分かるはず」と期待せず、むしろ、
きっと、また走るでしょ?
と、疑うことです。
期待は必ず、一瞬の油断につながります。事故はその瞬間起こります。
元気で手がかかるだけ…と軽く考えていたら、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
子どもにお任せできない。ということは──
子どもを変えるのではなく、大人の動き・関わり方を変えることから始める必要があります。
走り出しが起きたら、それは100%大人の責任です。
ここで言う“大人”とは、保護者である親御さん、そしてもちろん、支援者の私も含まれます。
出張カウンセリングでは、まずこのような強い心構えを共有することから、練習をスタートしています。
危険な行動は「叱る」よりも「練習」で防ぐ
が、頑張ります!でも何から始めれば良いのでしょう?
そう思うのは当然です。
今回のような相談は、過去に何度もお受けしてきました。
実際の練習風景や改善していく様子を、動画にたくさん残しています。
私の出張カウンセリングでは、その映像を見ながら「こうやって練習します」と、
親御さんに具体的なイメージをもっていただきます。
改善のポイントはとてもシンプルです:
- 絶対に離れない手のつなぎ方を覚えること
- とにかく“失敗しない”よう、スモールステップで練習を設計すること
この2点が全てです。
さらに、教育相談では、次の資料もお見せしながら、手のつなぎ方を丁寧に説明します。
1つ目は文庫ですぐに購入できますし、Kindleでもすぐに読めます。
2つ目は論文なので一般の方は手に取りにくいですが、実際の手のつなぎ方が、写真付きで分かりやすく解説されています。練習方法も丁寧に説明されています。
家庭でできる「手をつなぐ練習」の始め方
先生、どこでやりますか?家の前? 公園?
お家の中で始めましょう
え、ここで?
はい。家の中。それもたった2~3歩くらいの距離からスタートします。
よくある失敗は、最初から10m、20mといった距離で始めてしまうこと。
飛び出す・振り払う習慣のある子にこれをやると、
途中で手を離す、しゃがむ、逃げるといった“困った行動”がすぐに出てしまいます。
それに、もし道路で手を振り払われてしまったたら、
道路で親から逃げる練習を行ったことに等しいです。
1回の失敗がすべてを帳消しにする理由
親御さんによく言われるのが、こんな一言です:
でも、10mってそんなに長い距離じゃないですよね?
喝!!!
(注:絶対に怒りません。雰囲気だけ感じてください)
私たちがやろうとしているのは、「絶対に失敗させない」ための練習設計です。
子どもの反射神経、そして習慣の恐ろしさを侮ってはいけません。
自由に動きたい子どもが、手をつながれる。
それだけで、予想外の行動がいくらでも起きます。
私は、こんなふうに説明します:
目標距離が1mでも2mでも、手つなぎでうまく歩けたら1点。
でも、どんなに長い距離でも、最後の1mで手を振り払われたら、即マイナス100点です。
ということは、10回中9回成功しても…?
えぇ、最後に手を払って逃げられたら、マイナス91点。
ひえー💦
つまり、たった1回手を振り払われれば、何度もの成功を帳消しにする──
そんな行動だということです。
そりゃそうなんです。命がかかわっていますから。
だからこそ、ほんの数歩から。絶対に失敗させない練習構成で進めること。
これをできるだけ早く、できるだけ幼いうちに始めれば、外での飛び出しも無くせます。
「道路は手をつなぐ場所」という思考を育てる
もしこの練習を、歩き始めたばかりの頃から始めていたら──
子育ては、ずっとラクになります。
公園など安全な場所では走ってOK、でも道路や駐車場では“手をつないで歩く”が当たり前。
そんな子どもになると、発想そのものがこうなります:
え?道路って走っちゃダメでしょ?だって手、つなぐもん
これが、最強です。
1歳過ぎから相談を受ける場合は、最初からこの手のつなぎ方をお伝えしています。
すると、日常生活の中で自然と、「道路で走る」という選択肢自体が育たなくなるのです。
でも、実際の相談の多くは「もう手がつけられない…」というタイミングで始まります。
だからこそ、今すぐ取り組むしかないんです。
2歳くらいまでなら、道路で急に走り出しても、親が反射的に「ガシッ!」と止められるかもしれません。
でもこのとき、子どもの体験としては──
くそ、失敗か。もう少しで飛び出せたのに…
はい、まずい経験値がプラス1となってしまいました。
その後、3歳・4歳と年齢が上がるにつれ、状況はますます厳しくなってきます。
身長は15cm以上伸び、足も速くなり、判断も巧妙になります。
親の目を盗み、フェイントまでかけてくるようになります。
その頃には、親の体力は……そう、下降フェーズに入っています(悲しい…)
どんどん経験値を積む子どもVSどんどん膝に不安を抱える親
怒っても、注意しても、「重ねた経験値」には勝てません。
だからこそ、くどいようですが──
できるだけ早く、できるだけ幼いうちに支援を始めるべきなのです。
本当の課題は「大人のペース」で動けないこと
- 小さな子どもは、「ここは危ない」「ここは止まるべき」といった判断ができません。
- だから安全や命を守るために練習が必要。
これはもちろんその通りです。
でも視点を変えて、周囲の人や車を運転する人の立場で見ると、どうでしょう?
ルールもお構いなしに動き回る子どもがどう映るでしょうか。
──はっきり言って、危険で、迷惑です。
ちょっときつい言い回しですが、社会の目は厳しい。これも事実です。
「親と手をつないで歩く」という行動は、社会の中で過ごすための「基本の練習」です。
最初は窮屈に感じるかもしれませんが、大人と一緒に練習を重ねる中で、少しずつ慣れてもらわなければなりません
いわば、親子の必修課題なんです。
こういうとき、私は、
「大人のペース」って大事なんですよ
と、親御さんに伝えます。
「子どものペース」が親を苦しめる場面とは
「子どものペース」──これ、育児本やネット記事でよく聞きますよね?
でも実際には、“親にとって心地よく響く言葉”として使われることが多いのです。
親御さんが子育てで困るのは、ブランコと滑り台どっちで遊ぶか、ぬりえで何色を使うかといった、
子どものペースの場面ではありません。
- 夜寝る前、歯磨きをしようとすると、嫌だとかんしゃくを起こす
- チャイルドシートに座らせようとすると「ママの隣!(助手席)」と怒る
このような、本来は大人主導の場面なのに、子どもがそのペースに乗らない。
親が困るのはこういう場面のはずです。
そういわれると、他の場面でも思い当たることが💦
教育相談ではこういう話の流れになります。
実は今回の話。単なる“飛び出しの対策”ではなかったのです。それは──
「大人のペースで動ける力を、どう育てていくか」
という、子育ての土台の話でもあったのです。
今すぐ始めたい!飛び出し防止のための支援
出張カウンセリングでは、親御さんを責めるようなことは絶対にしません。
でも、「練習が必要ですよ」「ここは見直しのタイミングですよ」とお伝えする場面は、たくさんあります。
そういうとき、私は、「子育てのコーチ」のような立場で関わらせていただきます。
「大人のペース」、あなたはどう思いますか?
もしよければ、こちらの記事も参考にしてみてください。


他にはどんな相談を受けているの?――
そんな疑問がある方は、こちらのページもご覧ください。
当相談室は、千葉県・東京都エリアを中心に、出張カウンセリングを行っています。
今回のような練習も、専門家があなたのご自宅で直接支援します。お問い合わせはこちらからどうぞ。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。