支援が続く家庭・続かない家庭の違いとは?──ありのままをお話します
出張カウンセリングの仕事をしていると、
支援が順調に続いていくご家庭と、途中で止まってしまうご家庭があります。
その違いは、何でしょうか。
実は、お問い合わせの段階で、その“分かれ道”が見えることもあります。
まだ開業して間もない頃のことです。
当相談室へのお問い合わせは、ほとんどが「お母さん」からでした。
その際、私はいつも次のようにお尋ねしていました。
お父さんも、ご相談に同意されていますか?
すると、ここで返事が来なくなるケースが、意外と多くあったのです。
実際に数えてみると、およそ4割のご家庭が、その時点で連絡が途絶えてしまいました。
この経験を踏まえて、今では「ご家族の同意があること」を新規相談受付の必須条件としています。
詳しい内容はこちらからご確認いただけます。
👉出張カウンセリングの新規受付について
では、なぜここまで条件をはっきりさせているのでしょうか。
それは、「家族全員が、同じ方向を向いているかどうか」が、
支援が続けられるかどうかに直結するからです。
かつて「イクメン」という言葉が話題になった時期がありました(最近あまり聞きませんが…)。
でも、私が実際の現場で感じるのは、
父親が育児に関わっているかどうか──という話だけではありません。
それ以上に大切なのは、
「家族(夫婦)がひとつのチームとして、子どもの支援に向き合えているかどうか」です。
家族の足並みがそろわないときに起こること
支援が開始されても、途中で止まってしまう──
そんな場面に、私は何度も立ち会ってきました。
その背景には、ご家庭の中で“足並み”がそろっていない状態があることが少なくありません。
たとえば、こんなケースです。
初回のご相談には、ご夫婦そろって参加してくださったご家庭がありました。
2回目以降はお母さんお一人が出席する形になりました。
私はお子さんと直接関わりながら、ご家庭での対応についてもアドバイスをお伝えします。
ときには、次回までの“宿題”をお願いすることもあります。
ある日、その宿題の進み具合を確認すると、まったく取り組まれていないことが分かりました。
理由を尋ねると、お母さんは申し訳なさそうにこう言いました。
すみません、夫が「やらないでくれ」って言っていて…
実は、こうした出来事は珍しいことではありません。
ご家庭の中でどちらかがブレーキをかけてしまうと、支援はそこで止まってしまうのです。
別のご家庭でも、似たようなことがありました。
お子さんに発語の遅れや激しいかんしゃくがあるケースで、
私は言葉の練習とあわせて、ご家族の関わり方についてもアドバイスをしていました。
このご家庭では、お父さんが毎回のセッションに熱心に参加されていました。
けれど、お母さんはいつも少しうつむきがちで、あまり言葉を交わされません。
ある日ご自宅に伺うと、リビングにはお父さんとお子さんだけ。
お母さんは「体調不良」とのことで、お部屋にこもっておられました。
ですが、体調の問題ではないことは、分かっていました。
そこで私は、お父さんにこう尋ねました。
お母さんはもう相談を受けたくないのですよね?
お父さんは、しばらく黙ったあと、両手を合わせて「すみません」とだけおっしゃいました。
不満や意見があっても、自分ではそれを言わず、
結果として、大切なパートナーだけが矢面に立つ──
これでは、大切な家族の誰かが、板挟みの状態になってしまいます。
支援が前に進むには、「家庭がひとつの方向を向いていること」が必要です。
誰かがブレーキをかけている状態では、支援のみならず、子育てさえもうまく回らなくなってしまうのです。
家族関係が、支援の成否を左右する
支援がうまく進まないとき、
その原因が「お子さんの発達の課題」ではないケースが多々あります。
はっきり言えば、ご家庭の中の関係性そのものが、支援の進みに影響していることが少なくありません。
たとえば、こんな背景があるご家庭です。
- ご自身の両親と育児方針が合わず、夫婦の足並みもそろわない
- 話し合おうとすると、配偶者から否定ばかりされて、会話が成立しない
- パートナーと義理のご両親から「子育てがうまくいかないのは、あなたのせい」と責められている
このような状態では、家庭の中で対立や孤立がどんどん深まってしまい、
「子どものために協力しよう」という気持ちが機能しなくなってしまいます。
出張カウンセリングでは、こんな生々しい家庭内の構造まで見えてしまいます。
とてもプライベートな部分ですが、支援をするうえでは見逃せない現実がそこにあります。
私がこれまで支援を続けてきた中で、強く感じていることがあります。
それは、お子さんの「障害の重さ」や「特性そのもの」よりも、
家族の関係性のほうが、支援の難しさを左右することが多いということです。
家族関係がこじれてしまっていると、
どれだけ正しい支援を行っても、それが家庭の中でうまく機能しなくなってしまうのです。
支援に必要なのは、“リスペクトし合う関係”
家庭に出張して支援を行うと、ご夫婦の関係性が自然とにじみ出てきます。
ときには、教育相談の場で、配偶者への不満を口にされる方もいらっしゃいます。
もちろん、夫婦間で意見が食い違うのはどの家庭でも起こることですし、
冗談まじりに少し言いたくなる場面があるのも、よくわかります。
ですが、その“冗談”が、パートナーを下げるような言葉になってしまっているとき、
私は、その話題をやめるようにはっきりとお伝えします。
なぜなら、教育相談は、誰かを責めたり、笑いのネタにしたりする場ではないからです。
パートナーを軽んじるような言葉は、お子さんにとっても、支援にとっても、良い影響を与えません。
もちろん、どんなご家庭にもすれ違いはあります。
育児の中で、ストレスがたまってつい言葉が強くなる──
そんな日も、あると思います。
けれど、支援がうまく進んでいくご家庭には、ある共通点があります。
それは、「お互いを尊重しよう」という姿勢が、たとえ不完全でも、根っこにあることです。
すべてを完璧にできるご夫婦なんていません。
それでも、パートナーを信頼する言動がそこにあるかどうか──
そこが、支援の大きな分かれ道になります。
私は、教育相談の場で次のような声かけを意識しています。
ここまでやってくださるお父さん、なかなかいませんよ
お母さんが熱心に取り組まれたからこそ、今のお子さんの姿がありますね
こうした言葉は、単なる“お世辞”ではありません。
ご夫婦がリスペクトし合う関係に少しでも近づけるように──
そのような空気を作ることも私の役割と考えています。
当相談室の支援を受けようかどうか考えている方へ
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
今回の内容について、「少し耳が痛いな」──
そう感じられた方も、きっといらっしゃると思います。
それでもページを閉じずに、ここまで読んでくださったこと。
それ自体が、すでに大切なお子さんのことを、真剣に考えている証拠だと思います。
正直にお伝えすると、
当相談室で行っている支援は、「お気軽にどうぞ」とご案内できるものではありません。
子育ての悩みは、ときに家族関係の深い部分に触れますし、
専門家の支援を受けるには、ある種の“覚悟”が必要になることもあります。
私自身も、責任ある支援を行うために、軽い気持ちではお引き受けしていません。
だからこそ、こうしてブログを書いています。
事前に、私の考え方や支援に対する姿勢を知っていただきたいと考えているからです。
もし今、
「話を聞いてほしいな」
「この先生となら、いっしょに考えていけそう」
そんなふうに思っていただけたなら、それが何よりうれしいことです。
他にもいくつかの記事をご用意しています。
よろしければ、そちらもあわせてご覧ください。
👉 出張カウンセリングという形を選び続けてきた理由は、こちらの記事でも詳しくお話しています。


👉 お問い合わせから相談が開始されるまでの流れは、こちらをご覧ください。
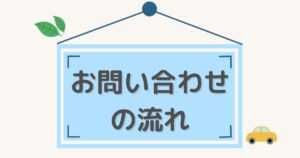
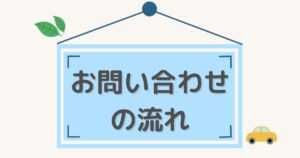
当相談室では、お子さんの発達や行動について悩まれているご家庭に対して、
専門家がご自宅に出張して直接支援を行います。お問い合わせはこちらから。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。


