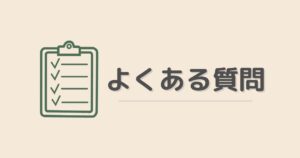言葉は出ているのに、コミュニケーションにならない…
子どもの療育支援や発達の相談では、ほぼ例外なく「言葉」に関する悩みが取り上げられます。
このブログでも、「言葉の遅れ」については何度も取り上げてきました。
関連記事はこちら
👉「2歳・3歳でも言葉が出ない理由」──発語を止めている“生活のパターン”とは?(前編)言葉が出な
👉専門家の「様子見でいいですよ」は本当?──支援が遅れる前に知っておきたいこと
さて、ある親御さんから、こんな相談がありました。
単語は出ているのですが…コミュニケーションにならないんです
私の教育相談では、初回の時点で、お子さんが無発語というケースが大半です。
そうした状態から見れば、「言葉が出ているだけでもありがたいのでは?」と思われるかもしれません。
ところが──
これはあくまで私の印象ですが、無発語でも変なくせがついていないお子さんのほうが支援しやすく、
逆に、中途半端に言葉が出ている場合の方が、かえって支援が難しいと感じることすらあります。
言葉が出さえすれば、それで“めでたしめでたし”ではなく、むしろ、親御さんの悩みが深まっていく。
今回はそんな話をしていきましょう。
まるで博士くん?単語がポンポンと出てくるけど…
たとえば、2歳半の男の子。乗り物が大好きで、毎日、車のカタログを眺めています。
きゅうきゅうしゃ!ぱとかー!すーぱーあんびゅらんす!
こんなふうに、教えたわけでもない難しい単語まで、スラスラと言える子もいます。
その姿はまるで、小さな博士くん。思わず感心してしまうほどです。
でも、ある日お母さんが「〇〇くん、きゅうきゅうしゃ走ってるよ!」と声をかけても──
彼は反応せず、明後日の方向を見ながら、ただ独り言のように車の名前をつぶやき続けていました。
すごいけど、ちょっと不思議…?
そう感じたとしても、この時点で支援を考える親御さんは、まずいません。
「言葉が出てるだけ良い」と思われることも多く、問題視されにくいのです。
ところが、年齢が上がってくると──
語彙は増えているのに、会話が成立しない。
という状況が、だんだんと明らかになってきます。
幼稚園や保育園では、お友達や先生との“やりとり”がうまくできず、
「この子、会話が通じない」という印象が、よりハッキリしてくるのです。
“中途半端に言葉が出ている”ことで──
- 支援が必要な子であると、気づかれにくい
- そのため、支援が遅れる
- 違和感があっても「様子見」の方向に転がる
結果として、早期の支援が入りにくく、介入のタイミングを逃してしまうケースも少なくありません。
コミュニケーションの「基礎」となる練習
たしかに、語彙は豊富かもしれない。
けれど、それが実際のコミュニケーションに使われていない。
せっかくお母さんが声をかけても、それにまったく反応しない。
これは、たとえ親子であっても、少し寂しい関係になっているな…と感じる場面です。
私の療育では、言葉やコミュニケーションの練習を行いますが、まず最初に取り組むのは次のような行動です。
親が声をかけたら、即座にパッとふりむいて反応する
親をしっかり見て、目を逸らさず、大人の動きについていく
こうした練習方法を親御さんにお伝えし、療育の初期段階から重点的に取り組んでいきます。
なぜなら、これらは──
発語だけでなく、人とのやりとりの基本となる、『肝心・要(かなめ)の行動』だからです。
ちょっと想像してみてください。
言葉がまったく出ていないお子さんでも、親御さんの呼びかけにいつでも百発百中で振り向くとしたら。
先ほどの博士くんよりも、こういうお子さんのほうが、実はずっと高いコミュニケーション能力を持っていると考えられないでしょうか?
このことを親御さんにお伝えすると──
確かに、いつでもすぐに反応してくれる方が嬉しいです。
と、深くうなずきながら納得されるのです。
おもしろく、そして人から愛される言葉を使う子にする
博士くんのようなタイプのお子さんは、発達検査でも平均を上回るスコアになることが少なくありません。
実生活では言葉のやりとりが独特なのに、検査になると言語面の得点だけが突出して高い──
そんなケースもよくあります。
こうしたお子さんへの支援では、
「みんなと同じようなコミュニケーションをできるようにしよう」とか、
「コミュニケーション上達のための訓練をしよう」といった発想は、基本的に持ちません。
苦手なことを、得意にするというのは、実際のところ難しいです。
では、何を考えるかというと「どういう言葉を使う子にするか?」という視点です。
尖ってチクチクするような言動ではなく、ちょっと変わっているけど丸い子になってもらうというイメージです。
たとえば──
家でご飯を食べるとき、どんなメニューが出てきても、
「このあじ、にがてだよーきらいなんだよー」
と言ってしまうお子さんがいました。子どもといえど、これは本当に嫌ですよね。
親御さんもいよいよ我慢できず、注意したり怒ったりするのですが、
それすらも面白がって、嬉しそうな表情を浮かべるくらいでした。
そこで、このお子さんとの出張カウンセリングでは、こんな練習をしました。
深みのある味付けに、芳醇な香り──今日の料理も絶品ですね!
このセリフを、“いただきます”の前に親子で必ず言うというお約束で、繰り返し練習しました。
また、別のケース──
他人の間違いをねちねちと指摘し、謝るまで許さないという癖があった女の子。
これも、人から確実に嫌われるパターンです。
このお子さんにはどうしたかというと…
カウンセラーの私が、わざと本の文字を読み間違え、ゲームのコントローラーを逆さに持ち、キャラクターも言い間違えるなど、失敗のオンパレードを、あえてやらかします。
その度に──
はぁ~なるほど、私とは別な視点で、なかなかユニークですね~
と、ちょっと大人びたツッコミを数パターン、ゲラゲラ笑いながら言うようになるまで練習しました。
ボケとツッコミの百本ノックみたいです。
幼少期の良い習慣が、悲しい未来の予防となる
このように、一見ふざけているように見えるやりとりが、実はコミュニケーションの練習だったりします。
ある場面やお題に対して、大人なら「プププ」と吹き出してしまうようなセリフを、
同年代の子どもたちにも「なんかよく分からないけど面白い」と感じてもらえるよう、言い回しを工夫していきます。
イメージは、笑点の大喜利のような世界です。
幼稚園生ですから、「深み」「芳醇」「視点」「ユニーク」なんて言葉の意味は分かっていませんし、
私も別に教えようとは思っていません。
(実は、子どもが普段使わないような表現の方が、変な癖が発動されにくいのです)
逆に──
人の間違いを指摘したり、批評家のように言葉尻を突いたりする癖は、間違いなく嫌われます。
言葉の使い方ひとつで、
好かれ、愛される未来にも、嫌われて孤立する未来にも分かれてしまう。
だからこそ、こうした支援は早期に取り組むことが大切です。
そして、こういった課題にこそ、支援者がご家庭に直接伺う「出張カウンセリング」が大きな力を発揮します。
お子さんの家庭での様子や日常の過ごし方に、教育目標のヒントがたくさん隠れているからです。
家庭の中だからこそ実現できた支援としては、以下の記事も参考になります。


「そもそも出張カウンセリングって何」?
そのような疑問を持たれた方は、こちらのページをご覧ください。
当相談室は、療育支援を専門とする専門家が、ご家庭に出張して相談をお受けします。
出張エリアは千葉県内・東京都内が中心です。お問い合わせはこちらからどうぞ。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。