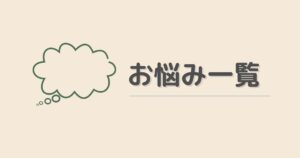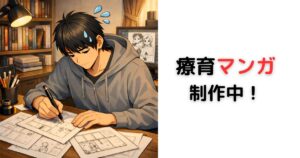こんなやりとり、毎日のように続いています
たとえば、「明日保育園ある?」って聞いてきます。
「あるよ」と答えると、「ほんとに?」と、また聞いてくる。「ほんとにあるよ」と言っても、「ママ、保育園あるって言ったよね?」と、5分後にまたまた同じことを…。
これが1回や2回ならまだしも、1日中、何十回も続くんですよ。
最初は「不安なのかな」と思って、できるだけ優しく答えていました。
でも、私の声に少しでもイライラが混じると、「いつもの言って!」と怒るんです。
親がつられて怒ってはいけないと分かっていても…やっぱり疲れます。
こういう“こだわり”には、どう対応したらいいのか、もうわからなくて——。
よくあるご相談です。一緒に考えていきましょう!
“同じ質問を何度も繰り返す”とか、「どうして?」をひたすら連発する。そういったパターン化されたやりとりに親御さんがうんざりしてしまう――そんな相談は、教育の現場ではよくある話です。
親御さんとしては、きっとこう思うはずです。
- 子どもの質問をむげに扱うのはよくない…。
- でも、これってちゃんとした“やりとり”になってるのかな?
- 何度も聞いてくるってことは、不安が強いのかもしれない…。
このように、どう接すればいいのか思い悩んでしまいます。
そんなとき、教育相談ではよくこんなふうに問いかけます。
- 「お母さん、どうしても忙しくて付き合ってあげられないときは、どうなりますか?」
- 「うんざりして、ちょっと適当に返してしまったこともあるかもしれません。そのとき、お子さんはどうでしたか?」
実は…ふてくされるだけじゃないんです。
癇癪を起こして、地団駄をふんで怒ることもあって…。
正直、そこまで怒らなくてもいいのに…と思うことすらあります。
今回の根本的な問題
「子どもがこだわりのように同じ質問を繰り返す」という相談は、
一見すると、“言葉”や“コミュニケーション”の課題に思えるかもしれません。
けれど、それは表面的な捉え方にすぎません。
本質的な問題は、もっと別のところにあります。
- 自分のこだわりに、他人を付き合わせてしまう。
- 思い通りのパターンにならないと、不穏になってキレる。
そういった習慣や反応のクセが、日常の中で根づいてしまっていることが大問題なのです。
そしてその習慣は、後々、より大きな影響を与えていく可能性があるのです。
イレギュラーは必ず起こります
特に、学齢期・思春期・青年期において、行動面での問題が大きいケースを担当している支援者であれば、きっと想像しやすいはずです。
たとえば——
- 何度も同じ言い回しを、相手に繰り返すよう求める
- 納得できるまで、やり方をしつこく確認し続ける
- 特定の場面やタイミングで、“決まったやりとり”を求める
このように、「お決まりのパターン」を相手に要求する傾向が見られるケースです。
もちろん、まわりの人がその要求に応えてくれる場面も少なくありません。
けれど、こんなことが起こったらどうでしょう?
- 担当の先生が急に不在になった
- 予定やスケジュールが変更になった
- いつもとは違うルートで目的地に向かった
- 置いてあるはずの物が、今日に限って見当たらなかった
そんなイレギュラーが起きて「お決まり」ができないとき——
パニックを起こす、癇癪を爆発させる、物や人にあたってしまう……。
支援の現場では、そうした“大荒れの場面”にたびたび直面します。
ただし、こうした反応は、幼児期から適切な練習や関わりを重ねていくことで、予防することが可能です。
この記事でお伝えしているのは、まさにその“予防の第一歩”についてです。
うちの子は、2歳の頃に「自閉傾向があるかもしれません」と言われていて…。
だから今回のようなことも、「言葉やコミュニケーションの弱さ」から来ているのかなと考えていました。
でも、今のお話を聞いて、もっと根深い問題があるのかもしれない…と感じました。
“いつも通り”が通じない社会の中で
多くの親御さんは、「子どもの質問にどう答えてあげればいいのか」と考えるとき、
無意識に「子どものペースに合わせてあげるべきだ」という前提がセットになります。
でも、実はその反対の視点も、とても大切なんです。
- 相手はいつも、丁寧に答えてくれるとは限らない
- 自分の思った通りの返事が返ってこないこともある
- 楽しかった会話が、突然中断されることだってある
――これが、社会の中で起きる“普通のこと”です。
たとえば、朝の忙しい時間。お母さんは子どもの質問すべてに付き合えませんよね。
幼稚園や保育園の先生だって、一度にたくさんの子どもを見ているなかで、いつもこちらの意図をくみ取ってくれるとは限りません。
子どものこだわりとどう向き合うかを考えるときには、「社会のリアル」を視野に入れていなければなりません。
次回予告:“パターン崩し”と“こだわり崩し”の練習方法
では実際に、どんなことをしていくのか。
次回は、子どもの“こだわりパターン”に対して、どのように関わり方を変えていけばよいのか――
「パターン崩し」「こだわり崩し」の練習方法についてお伝えします。
同じ質問を何度もしてくるお子さんには、これまでと同じ答え方では通用しないことがあります。
だからこそ、少しずつ異なる関わり方を試し、練習していく必要があるのです。
後編では、実際に親御さんにお伝えしている具体的な関わり方の例をご紹介します。
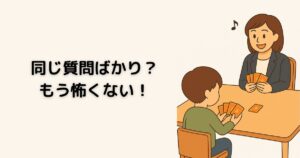
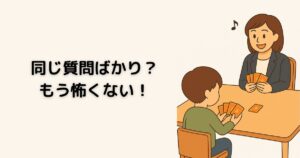
出張カウンセリングでお受けする相談は、本当に様々です。
「どんな相談があるのだろう」と思われた方は、こちらをご覧ください。
当相談室は、千葉県・東京都エリアを中心に、出張カウンセリングという形で療育支援を行っています。
専門家がご自宅にうかがい、お子さんへの直接指導と親御さんに具体的なアドバイスをしています。
出張相談を希望される方は、こちらよりお問い合わせください。
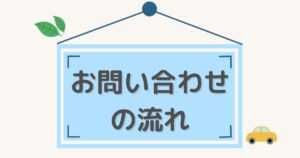
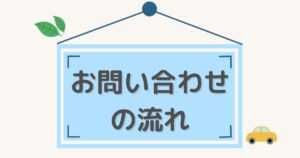
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。