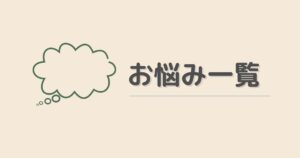今日は、ちょっと変わったテーマについて書いてみます。
教科書にも、子育て本にも載っていない。けれど、支援に関わる人なら必ず一度は立ち止まる問いです。
少し堅めの内容かもしれませんが、できるだけやさしく、現場の言葉で綴っていきます。
肩の力を抜いて、気軽に読み進めてみてください。
臨床心理士の現場で求められる、信頼よりも重要なもの
臨床心理士としての私は、さまざまな立場の人と関わります。
- 子どもへの直接的な支援
- 保護者へのアドバイス
- 教育現場の先生へのコンサルテーション
- 他の支援機関への助言
つまり、向き合うのは「子ども」「親」「教師」「支援者」と、多岐にわたります。
このような関係者を、臨床の場では「クライアント」と呼んでいます。
臨床心理士の教科書には、こうあります。
「カウンセリングでは、カウンセラーとクライアントとの間で信頼関係を築くことが大切です。」
ここで、あえて問いを立ててみましょう。
——カウンセラーは、クライアントを信頼していいのか?
私の答えは、はっきりNoです。
支援者失格と思われるかもしれません。
下手をすれば、業界から追放されかねない発言でしょう。
それでも私は、明確に「No」と答えます。
信頼を“前提”にしてはいけない——現実はもっとシビアです
これは、クライアントを見下しているとか、自分が優れているとか、そんな話ではありません。
むしろ逆です。支援の現場に立つなら、一度は冷静に考えるべき問いがあります。
たとえば——
保護者にアドバイスをしたとき、返ってくる言葉はたいてい「やってみます!」。
「やりません」とは、まず言われません。
では、そう答えたからといって、
「次回までにやってくれるだろう」と思い込んでいいのでしょうか?
もう一つ。
ある子が、日常的に親を叩いていたとします。
私が丁寧に伝えます。「やめよう。先生と約束しよう」
子どもは泣きながら「うん、もう叩かない」と応えます。
では、もう叩かないのでしょうか?
——答えは、Noです。
保護者の多くは、やってくれません。
子どもも、また叩きます。十中八九。
支援者が直面する“裏切られた感覚”と、その正体
「アドバイスをしたのに実行されない」
「約束したのに守られない」
支援に関わる人なら、こうした場面に必ず直面します。何度もです。
そのたびに湧き上がる感情は——
- あれだけ丁寧に伝えたのに…(落胆)
- 私の説明が悪かったのか…(自己嫌悪)
- 守らなかった相手が悪い!(怒り)
- この人には、何を言っても無駄かも(諦め)
これらをまとめると、こう言えるかもしれません。
——裏切られた。
そう感じるのです。
信じたのに、返ってこなかった。その反動です。
でも、視点を変えてみてください。
クライアントの側から見たら、どうだったのでしょう。
「大きなお世話だ」
——そう思われていたとしても、不思議ではありません。
疑う力は技術であり、鍛えるべき“専門性”の核である
私は、ある先生のもとで長く学んできました。
教科書には絶対に載らないけれど、現場では手放せない——そんな問いを、何度も投げかけられてきました。
「どうしてクライアントを信用したのか?」
「なぜ、疑わなかったのか?」
「子どもを疑いなさい。親を疑いなさい。そして——自分自身も疑いなさい。」
最後のこの言葉は、今でも私の支援の根幹にあります。
たとえ、親御さんにアドバイスを一つするだけでも、私は自分に問いかけます。
- やってくれる保証はあるのか?
- 実行したかどうか、どう確認する?
- このお願いは現実的か?
- 忙しさや家庭環境を想像できているか?
- 他の家族が「やらない」と言い出したら?
- 継続できるような支援体制はある?
- もし失敗したとき、次の手は?
これらの問いを自問し尽くして、ようやく私は「アドバイス」という言葉を発するのです。
疑うことは、疑念ではなく技術です。
支援の専門性は、この“疑い抜く姿勢”そのものに宿ると、私は思います。
「信頼」は到達点であり、出発点ではない
『クライアントとの信頼関係』
『クライアントを信じる』
——カウンセリング界隈では、このような言葉が、まるでおまじないのように使われます。
でも私は、これらを軽々しく口にすることはできません。
むしろ、こう思っています。
- 私の言葉なんて、相手には届かないかもしれない
- 不信や疑念を抱かれる?当然のこと
- 口約束が守られる?そんな保証、どこにもない
これが、私の支援の“出発点”です。
ここからしか、始められない。
だからこそ私は、支援をこう設計します:
- アドバイスは可能な限り、具体的に
- 実行状況の確認方法もセットで提案
- 母親だけでなく、父や祖父母も巻き込む体制を整える
- 破られる約束は、そもそも交わさない
- 問題行動が“起きにくい”環境づくりを優先する
相手を疑う。自分自身も疑う。
その上で、あらゆる準備と想像力を尽くす。
私は思います。
臨床家の技量とは、この“疑う力”に比例するのだと。
疑った先にこそ、生まれる感謝と驚き
では、深く深く疑い抜いた先に、何があるのでしょうか。
——それは、感謝と驚きです。
支援の現場で、こんなふうに感じる瞬間があります。
- 難しい提案を、保護者が受け入れてくれた
- 実行してくれたおかげで、子どもに変化があった
私はそのたびに、心から「ありがとうございます」と伝えたくなります。
そして子どもには、「よく頑張ったね」と、全力で称えたくなるのです。
なぜなら、私の支援の出発点にはいつも——
「やってくれるわけがない」という前提があるからです。
だからこそ、ほんの少しでも行動が変わったとき。
たった一度でも、約束が守られたとき。
「……本当にやってくれたの?」
「すごい、よく頑張ったね」
そんなふうに、驚きと敬意とともに、支援者としての感動が湧いてくるのです。
“非常識”に見えるその視点こそ、支援の本質かもしれない。
子どもを疑い、親を疑い、そして自分自身さえも疑う。
そんな考え方は、一見すると冷たく、非常識に思えるかもしれません。
でも私は、それが支援の出発点として欠かせない視点だと信じています。
なぜならそこには——
- 無理を押しつけず、できる範囲を見極める視線があり
- 約束の重みと現実の限界を知る姿勢があり
- 相手に過度な期待を背負わせない、誠実さがあるからです
“疑い”を通してこそ、見えてくる希望があります。
この視点に立った支援が、実際にどのように行われているのか。
もし興味を持たれた方がいれば、ぜひこちらをご覧ください。
実際に支援を受けたご家庭の声の中に、“現実”と“可能性”の両方が映っているはずです。
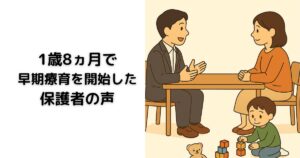

日々こんなことを考えながら支援しています。
「相談室ではどんな悩みが寄せられているのかな?」
——そう思われた方はこちらが参考になります。
当相談室は、専門家が行動分析学に基づいた支援を行っています。
ご家庭への出張カウンセリング希望される方は、こちらからお問い合わせください。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。