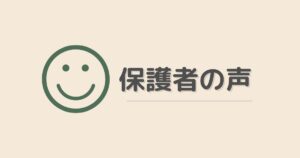発達支援を受けようと思うきっかけ——セカンドオピニオン
親御さんが私の相談室に問い合わせてくださるとき、そこには何かしらのきっかけがあります。
たとえば、1歳半健診や保育園での指摘をきっかけに相談される方も少なくありません。
ですが実は、すでに別の支援機関で相談を受けている方が、
「今受けている支援に、ちょっと疑問を感じていて……」
と話してくださるケースも、意外と多いのです。
つまり、支援機関を探す理由の中には、“セカンドオピニオン”としての意味合いが含まれている場合もあるということです。
今回は、そうしたご相談の中でも特によくあるケースをご紹介します。
お母さんは外で…
ある支援機関に通い始めた、親子のお話です。
ヒアリングを終えて、いよいよ個別の指導が始まりました。
初回は、お母さんも一緒に同席してスタート。
しかし、指導が進むにつれて、子どもは「ママ、ママ!」と落ち着かなくなり、お母さんから離れられなくなってしまいました。
その様子を見た指導員の方は、「モニタールームがありますので、そちらで見ていてください」と、お母さんを別室に案内したそうです。
次の回も同様に、お母さんは別室での見学に。
けれど、子どもはすでに「ママが隣にいる」とわかっていて、指導が始まるなり部屋を飛び出し、モニタールームに向かってしまいました。
その後、指導員はこう伝えたといいます。
「お母さんも普段お疲れでしょうから、指導中は外でゆっくりされてくださいね」
結果として、お母さんは終了10分前まで、事業所の外で待機するよう案内されることになりました。
こうしたことが何度か続き、
「何かが違うかもしれない…」
と感じたお母さんが、私の相談室に連絡をくださいました。
私にとっては、「またこのパターンか」と思うくらい、よくあるご相談です。
そして私はこうお伝えしました。
本来なら、絶対に同席しておく場面だったと思います
指導員にとって、母同席が“やりにくかった”理由とは?
実際に保護者の方が支援機関で聞いた言葉をご紹介します。
- 「お母さんがそばにいると、落ち着かなくなるのかもしれませんね」
- 「今は“プログラム”をきちんと進めることが大切なので…」
一見するともっともらしく聞こえますが、ここで少し立ち止まって考えてみたいのです。
そもそも、その“プログラム”とは何なのでしょうか?
多くの支援機関では、「このタイプのお子さんにはこのメニューを」というように、あらかじめ定められた指導内容があります。
支援者としては、そのメニュー通りに子どもが取り組めないと「指導が進まない」と感じてしまうのかもしれません。
けれども、今まさに起きている「お母さんが近くにいると支援者との活動が成り立たない」「声かけに応じられない」といった状態こそ、まさに支援の出発点となるべきではないでしょうか。
それは、まさに家庭で保護者が「困っている」と感じている場面と重なっているはずです。
けれど、実を言えば——
現場では、お母さんの前で崩れてしまう子どもへの対応に、戸惑っている支援者も少なくありません。
うまくいかない様子を親に見られるのがつらい、という声も、これまでに何度も聞いてきました。
正直なところ、「見られたくない」「どうしたらいいかわからない」と感じているのは、支援者自身だったりするのです。
でもその本音は、あまり語られません。
代わりに、「母子分離のほうが効果的かもしれませんね」といった“もっともらしい理由”に置き換えられてしまう——
そんな構造が、あるのです。
支援プログラムは、生活の実態をふまえて組み立てられる
支援の目的は、親子の「生活の質」を高めることにあります。
支援室の中で“うまくできるようになること”ではありません。
今回のように、「お母さんが近くにいると行動が乱れる」のであれば、
むしろお母さんのそばでも落ち着いて過ごせるようになることを支援の目標とすることが大切だと思うのです。
外でうまくできても、家に帰ったら何も変わっていない。
そんなギャップに、日々悩んでいる保護者の方は少なくありません。
だからこそ、考えるべきなのは、こういった問いです。
この親子は、支援室を出たあと、どんなふうに過ごしているのだろう?
家の中では? 保育園では? 一日の中で、どんなやりとりがあるのか?
そうした日常の中で起きていることに目を向けずに、「支援が進んでいる」と言えるでしょうか?
何より、保護者が同席していなければ、こうした“生活の実態”は見えてこないのです。
日常を丁寧にひもといていく支援の考え方を、専門的には「生態学的アセスメント」と呼びます。
これは、ご家庭がどんな暮らしをしているのか、どんな場面で困っているのか——
その“リアル”を出発点に支援を組み立てるという方法です。
そして——
効果的な支援ができるかどうかは、この“リアル”の見え方に、かかっています。
保護者が本当に望んでいること
多くの親御さんが支援機関に足を運ぶとき、
「支援室の中で“いい子”になってほしい」と思っているわけではありません。
本当に願っているのは、もっと切実で、もっと日常的なことです。
- 家で、もう少し落ちついて過ごせるようになってほしい
- 追いかけっこにならず、親子で街をゆっくり歩きたい
- かんしゃくではなく、穏やかな声こそ聞きたい
そんな思いを抱えて、ようやく重い腰を上げて、相談に来られているのです。
1週間は168時間。
支援機関で過ごす1時間は、その残り167時間につながっていなければ意味がありません。
けれど、私の相談室に来られる方の中には、こんな声をよく聞きます。
「支援機関に行ったけれど、生活に関するアドバイスは何ももらえなかった」
「“ここでは問題ありません”って言われたけど、家ではまったく変わっていないんです」
そんな言葉を聞くたびに、私は思います。
「支援がうまくいっているかどうか」は、支援室を一歩出てからわかるものだと。
最後に——
今回お伝えしたかったのは、
「保護者が支援場面に同席すべきかどうか」という“形式”の話ではありません。
もっと本質的な問いとして、
支援とは、レストランのメニューのようにあらかじめ決まっているものではない
ということを考えたかったのです。
用意された既製品を並べるのではなく、
目の前の子どもや保護者の“今”に合わせて、その都度手づくりしていくもの。
私は、そう信じています。
いま目の前にある子どもの課題も、
保護者の方への助言も、
すべてはそのご家庭の「生活の実態」に軸足を置いて、オーダーメイドしていく。
それが、本当の意味での「良い支援」だと私は思います。
その考えから、私は出張カウンセリングという形で、
実際の暮らしの場にうかがいながら支援を行っています。
もちろん、通所を否定しているわけではありません。
大切なのは、どこで行うかではなく、
その支援が、ちゃんと“生活”につながっているかどうか。
この記事が、「何かが違う」と感じている方の中で、
その“違和感”を言葉にするきっかけになれば嬉しいです。
専門家に相談していても、不安が拭いきれない…
そのような違和感がある方には、こちらの記事も参考になります。


子育ての先輩たちはどんな気持ちで支援を受けていたのだろうか――
そんな疑問がある方は、こちらのページもご覧ください。
当相談室は、千葉県・東京都エリアを中心に、出張カウンセリングを行っています。
専門家がご自宅までうかがい、家庭の中で支援を行います。お問い合わせはこちらからどうぞ。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。