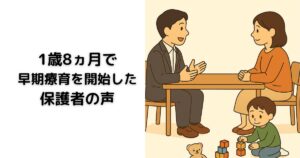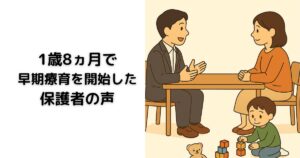1歳8ヶ月。周りの子は話し始めているのに、うちはまだ…。
市の相談に行っても『様子を見ましょう』と言われ、出口の見えない不安の中にいませんか?
この記事では、同じ悩みを抱えていたお母さんが、
どうやって『様子見』の壁を突破し、1年後におしゃべりな子へと変わったのか、
そのリアルな軌跡をご紹介します。
親御さんの言葉は、加筆・修正せず、原文そのままを掲載しています。
1歳8ヶ月で「言葉が出ない」不安──違和感を信じて踏み出した一歩
1歳8ヶ月の時に相談しました。
1歳過ぎても⾔葉が出てこないことに加え、「人の顔をあまり⾒ない」「つま先歩き」など、
息子の⾏動に違和感を持っていました。
児童センターなどで遊んでいても、お友達とリトミックなどは苦手で、
抱っこを求めたり固まって動かなくなったりしていました。
指差しや簡単な指示動作はできていましたが、コミュニケーションの取りづらさを感じていました。
【解説】1歳8ヶ月の「違和感」は、早期支援を開始する最高のタイミング
この事例で最も重要なポイントは、1歳8ヶ月という早い段階で支援を開始したこと。
これに尽きます。
言葉の遅れに気づいたとき、多くの親御さんの前に「3つの壁」が立ちはだかります。
- 身近に相談できる場所が見つからない
- 不安が強すぎて、どう動けばいいか分からない
- 家族の間で「まだ大丈夫」「気にしすぎ」と意見が割れる
これらも切実な問題ですが、一番もったいないのは、
勇気を出して相談した先で言われるこの言葉です。
実は、今回ご紹介している親御さんも、最初は行政の窓口でこのように言われていました。
市の発達相談で療育の相談をしましたが、幼いため様子をみることを提案されました。何もしていない事が苦しく耐えがたい時間でした。
しかし…
発達障害を検索する中で、早期療育の有用性を感じていたため、将来の自分達のために療育を受けようと決⼼しました。
専門家が言う「様子見」は、時に支援の先送りを意味します。
この親御さんは、専門家の言葉を鵜呑みにせず、自分の直感を信じて一歩踏み出しました。
この「様子見をしない」という決断が、お子さんの未来を大きく変える分岐点となったのです。
👉専門家の「様子見でいいですよ」は本当?──支援が遅れる前に知っておきたいこと
「言葉を教える」その前に。最初に取り組んだのは「泣きへの対応」でした
親御さんにとっての切実な願いは「言葉を話してほしい」ということです。
しかし、専門的な視点で見ると、言葉が遅れる「真犯人」が別にいる場合があります。
⾔葉を話して欲しいことが一番だったので、最初に⾔葉の遅れについて相談しました。
初回相談で息子は 90 分間泣き続けました。
⾔葉を話すためには、泣いて要求を通すことをやめさせる必要性があることや
泣いている時の対応を教えて頂きました。
【解説】激しい興奮・かんしゃくが言葉の発達にブレーキをかける
私の療育では、子どもを怒ったり叱ったりすることは、一切ありません。
できない課題を無理やりやらせることもしません。
初めて見知らぬ人が来たわけですから、子どもは、もちろん緊張します。
しかし、安心できる家ですし、お母さんはすぐ近くにいます。
90分間泣き続けてしまうという状態は、
興奮やかんしゃくが「言葉を使わなくても自分の思いが通る手段」
になってしまっているサインでもあります。
教育相談では、どうしてここまでかんしゃくが強くなってしまったのか、
その理由とこれからやるべきことを、親御さんに知っていただく必要があります。
息子への接し方が⼤きく変わりました。⾏動変容を促すために必要な接し方を教えて頂き家族で情報を共有、一貫した対応をするようにしています。
このように、家族が一致団結して取り組んでくれました。
その結果──
息子は相談してから半年ほどで⼆語⽂を話すようになり、
2歳8 か月の現在は、自分の気持ちを伝えられるようになり、とてもおしゃべりです。
以前より泣くことが減り、気持ちをコントロールすることが上手になってきていると感じています。
この劇的な変化は、親御さんがお子さんと正面から向き合い、
という厳しい現実を素直に受け入れ、実践してくださった結果です。
激しい興奮・かんしゃくの問題点は、こちらの記事でお伝えしています。
👉2歳・3歳で言葉が出ない原因は“2人の犯人”──支援現場で分かった意外な落とし穴(後編)
👉「すぐ怒る」「かんしゃく」には、何ひとつ良いことがない──2歳から“キレる習慣”を断ち切る療育
言葉だけじゃない──「手繋ぎ」や「トイトレ」までスムーズに進んだ理由
言葉が出てくればそれで「おしまい」ではありません。
実際の相談では、「外出時のルール」や「身の回りのこと」など、気になることが他にも出てきます。
「手を繋いで歩く方法」「トイレトレーニング」など⽇々の⽣活で困っている⾏動や気になったことをその都度相談しています。
保育園では集団⾏動をせず一人で遊んでしまうこともある様ですが、
お友達と追いかけっこしたり、手を繋いで散歩に⾏ったりと楽しく登園できています。
【解説】生活の「困りごと」にすぐ対応できる、継続支援の強み
「言葉が出れば、支援は卒業」というわけではありません。
むしろ、子どもが成長すれば新しい悩みが出てくるのが普通です。
- 「急に走り出す」「道路で手を離す」など、外出時のヒヤッとする場面
- 「トイトレを始めたいけれど、言葉がまだだし…」という迷い
こんな時、早期から関わらせていただいている効果が発揮されます。
私はすでにお子さんの「行動のクセ」や「ご家庭の環境」を把握しているので、
何かが起きた時に「今すぐできる具体的なアドバイス」をピンポイントでお伝えできるのです。
さらには、「次はこんな壁にぶつかるかもしれません」と予測して、
トラブルが起きる前に先手を打つ「予防」まで可能になります。
具体的にどんな言葉で親御さんに支援したか──こちらの記事が参考になります。
👉3歳児が外で急に走る──道路や駐車場での“飛び出し”を防ぐ練習と考え方
👉3歳で言葉が出ない…それでもトイトレは始められる?──「しゃべれるようになってから」は誤解です(前編)
お子さんの発達や行動に悩んでいる方へ
最後に、今回体験談を寄せてくださった親御さんから、今まさに悩んでいる方へのメッセージです。
相談するようになってからは、経験に基づいた⽀援を受けられ、将来を⾒据えた子育てが出来るようになりました。
お子さんの発達⾯や⾏動⾯に不安を感じている親御さんは、苦しい気持ちを抱えていらっしゃると思います。
ご家族だけで悩まず、まずは専門家に相談してみてください。
貴重なお話をありがとうございます。
早期支援の“早期”とは?──当相談室が「3歳未満」にこだわる理由
- 周りに相談できる人がいない
- ネットで調べても、わが子に合う方法が分からない
そんなふうに、ひとりで抱え込んでいませんか?
今回ご紹介したご家族も、最初は同じように不安や迷いの中にいらっしゃいました。
でも、「このまま様子を見ているだけでいいのだろうか」という直感を信じ、
最初の一歩を踏み出したことが、現在の「おしゃべりな息子さん」との楽しい毎日に繋がっています。
当相談室では、「早期支援」こそがお子さんとご家族の未来を守ると考えています。
そのため、新規のご相談は「お問い合わせ時点で3歳未満」のお子さんに限らせていただいています。
これは、「3歳を過ぎたらもう遅い」という意味ではありません。
不安を感じたら、様子を見ることなく、すぐに早期に支援を開始すべき
という決意表明からです。
子どもの発達に「待った」はありません。
「相談するには早すぎるかも」と迷っている今こそが、
お子さんにとって、そしてあなたにとって、最も大切なタイミングです。
「うちも一度相談してみようかな」と思われた方は、どうぞご連絡ください。
初回の相談から、今の状況を丁寧に伺い、一緒に整理するところから始めます。
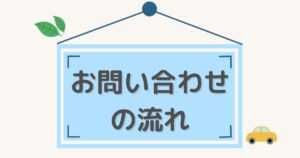
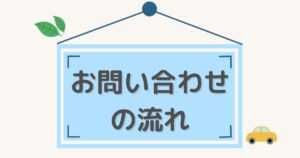
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。
実際に相談された方の声を知りたいという方は、こちらをご覧ください。