「言葉の遅れ」の悩みについて出張療育の専門家が解説します
私の仕事は、親御さんから子育ての悩みをお聞きして、ご家庭に直接出向いて支援することです。
悩みは色々ありますが、その中で一番多いのは──
言葉が出てきません……
このような、言葉やコミュニケーションに関するお悩みです。
ちなみに、過去10年分のお問い合わせを振り返ってみたところ、
その全てに「言葉が遅い」「発語がない」といった悩みが書かれていました。
それほど、言葉の遅れは、親御さんにとって最も切実な悩みですし、
療育支援を語る上では絶対に避けて通ることのできないテーマと言えます。
今回、「もうすぐ3歳なのに言葉が出ない」という不安に対して、
前編と後編に分けて解説記事を書きます。
前編では、応用行動分析学(ABA)に基づいて支援を行う私が、
ご家庭に初めて出張して「言葉の悩み」の相談をお受けしたとき、何を考えているかについてお伝えします。
出張療育の専門家として、“普段の暮らし”のどこを見ているのかを解説します。
次に後編では、発語やコミュニケーションを停滞させてしまう具体的な原因と、
それを取り除くために何が必要かを明らかにします。
特に、なぜ早期に支援を開始することが大切なのかをお伝えします。
発語のヒントはどこにある?──普段の生活の中に必ずあります
初めて支援者が家に来る日は、親御さんもドキドキです。
一体何をするんだろう…
と、親御さんは不安に思われているはずです。
一方、支援者である私が訪問先のご自宅で何を考えているかというと——
このご家族は、普段どんな毎日を過ごしているんだろう?
極端に言えば、これしか考えていないと言ってもよいほどです。
それくらい注目しているのは──
「生活」
つまり、「ありのままの暮らし」です。
このお子さんは、まだ発語がない、言葉が遅いのかもしれませんが、
生活の中には、言葉を使うべき「相手」「場所」「タイミング」などが必ずあります。
そのような機会(チャンス)がどれくらいあるのか、
そして、音声の言葉を使っていないのであれば、他のどんな手段を使っているのか。
言葉を引き出すカギは、どこか特別な場所ではなく、
ふだんの暮らしの中にこそあるのです。
言葉の獲得の支援で、最初にやること──生活の実態調査
たとえば、ジュースを飲むのが大好きなお子さんがいたとします。
二語文どころか、まだ単語も出ていない“無発語”の状態としましょう。
普段、どうやってジュースをもらっているんだろう?
こんな疑問が湧いてきます。
出張による療育支援では、このリアルな現場を見ることができます。すると──
- お母さんの腕をグイッと引っ張る
- 「アー!アー!」と大きな声を出す
- 持っている積み木をお母さんに投げる
なるほど…
このように、少しずつ生活の実態が明らかになってきます。
- 何に興味があるのか、どんなふうに遊ぶのか?
- 好きな食べ物・飲み物は何だろう?
- 誰と、どんなふうに関わっているのか?
名探偵コナンは、事件が起こると現場で情報収集を始めますが、出張の療育も全く同じです。
家族の“生活の現場”をよく観察して、言葉の発達に関するヒントを拾い集めていくのです。
言葉の発達を止めてしまう原因は、生活の中から見つかる
言葉の獲得にあたっては、「生活」「ありのままの暮らし」をよく見て調査することから始まります。
先ほどはジュースを例に挙げましたが、もちろんそれだけではありません。
観察するのは、好きなもの、家族とのやりとり、物の配置など、まさに家庭の全てです。
すると──
- ピタゴラスイッチが好き? 誰が、いつ、どんなきっかけでテレビをつけている?
- ぬいぐるみを絶対に離さない? お母さんが洗濯に出したら、どんな反応をする?
- さっきまでずっと泣いていた子が、親の近くに寄ってきて、地団駄を踏み始めた…
こうしたひとつひとつが積み重なることで、あることがはっきりと浮かび上がってきます。
それは──
言葉を学習しなくても生きられる生活になっている
という構図です。
言葉を学習しなくても、欲しいものは手に入るし、やって欲しいことも叶う。
親御さんの悩みや不安はよそに、子ども自身の日常生活は成り立ってしまっている。
言い換えれば、その子にとって、
「言葉を覚える必要がない環境」になってしまっているのです。
これこそが、言葉の発達を止めてしまう最大の原因なのです。
次回予告:言葉の発達を遅れさせる“黒幕”とは?
どうしたら、この子は喋れるようになるんでしょうか?
この質問にお答えすると──
もちろん、その子に合わせた言葉の練習が必要です。
椅子に座って行うスタイルの練習もありますし、遊びの中での練習もあります。
練習で学んだことを普段の生活の中でも使えるようにすることが大切です。
これが家庭の中ですぐにできることが出張療育の強みです。
しかし、練習によって言葉が身に付く力を持っていたとしても、
「言葉を学習しなくても生きられる生活」が変わらなければ、根本的な解決には至りません。
言葉の獲得を邪魔する原因を生活から取り除くこと
前編でお伝えしたかったのは、結局この一点です。
次回の後編では、発語やコミュニケーションが遅れてしまう原因と、
それにどう対処すればよいか解説します。
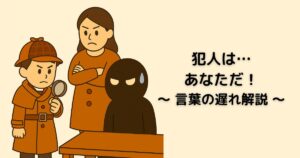
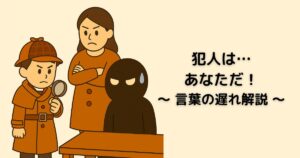
言葉の遅れているお子さんに「これは絶対にダメ!」という関わりもあります。
こちらの記事で紹介しています。


当相談室は、千葉県・東京都エリアを中心に、専門家がご自宅にうかがう形で支援を行います。
応用行動分析学(ABA)に基づく支援を受けたい方は、こちらからどうぞ。
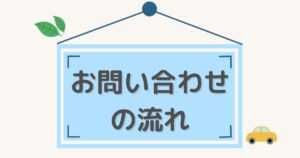
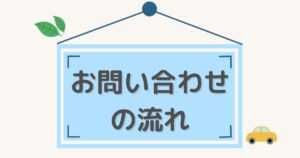
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。








