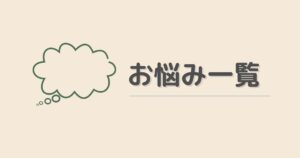言葉が出たのに、育児が楽になるどころか苦しくなった──
そんな親御さんに届けたい、支援の現場からのヒントです。
「言葉さえ出れば、きっと楽になる」と思っていませんか?
出張カウンセリングで出会うお子さんは、その多くが無発語です。
実際、私が初めての相談でお会いした段階で、しっかりと話せているお子さんは、ほとんどいません。
もちろん、そういった場合には、発語やコミュニケーションの支援を行います。
そして、少しずつ言葉が出始めたとき──
「ママ」と呼んでくれたその瞬間、涙ぐむ親御さんもたくさんいます。
私自身も、何度この場面に立ち会ったかわかりません。
そのたびに、「この仕事をしていてよかった」と思います。
でも、その喜びも束の間——
新たな壁が、目の前に現れることも珍しくないのです。
それは、
「イヤ!」「ヤダ!」「ダメ!」「ブー!」
…感動の第一声のあとは、まさかの拒否のオンパレード。
言葉が出るようになっただけでもありがたい…
最初は、そんなふうに思っていたのですが、
でも、これが毎日、あらゆる場面で続くようになると……心が持たなくなります。
- 何を言っても「イヤ!」
- 食事もお風呂も「ヤダ!」
- 保育園の準備も「パパはヤダ!」
「どうせイヤって言うから…」と、大人が譲る場面が当たり前になっていき、
気づけば、子どもの機嫌が家庭の方針になっている。
せっかく言葉が出たのに、
楽になるどころか、かえって苦しくなる。
そんな状況が、お問い合わせのきっかけになることも少なくありません。
2歳・3歳は、子育て最大の分岐点
世の中ではよく「イヤイヤ期」と呼ばれる2歳・3歳の時期。
けれど、長年療育の現場にいて、数多くのご家庭を見てきた私にとっては、
この時期はもっとはっきりこう呼ぶべきだと思っています。
子育ての最初の、大きな分かれ道です
この時期の親の関わり方は、
その後の子育て全体の“軌道”を決めてしまうほど、大きな影響を持ちます。
私は相談のなかで、こうお伝えすることがあります。
今のままだと、親が“召使い”になってしまいますよ
強い表現に聞こえるかもしれません。
でも、この時期の関わり方によっては、
「親が要求にすぐ応じるのが“当たり前”になり、気づけば子どもに振り回されている」
という状況に発展していくことがあります。
それがどんなふうに現実になるのか──
ぜひ、こちらの記事もご覧ください。
👉 「ふりかけがないと食べない」からの脱却──“偏食”ではなかったA君と親の再スタート
このケースは、私の教育相談を受けた親御さんが
「ぜひブログで紹介してほしい」と強く希望されたことをきっかけにまとめたものです。
読んでいただければ、
“子どもに合わせすぎること”が、どれほど家庭のバランスを崩すのか、
そして、そこからどう立て直すか──そのヒントがきっと見つかるはずです。
子どもにどんな態度で接すればよい?
出張カウンセリングで、よく受けるご相談があります。
「朝、保育園に行こうとすると『パパはイヤ!』と泣き叫ぶんです」
「チャイルドシートに乗せようとすると、大泣きで大暴れします」
そんなとき、私はすぐに「こうしてください」と答えることはありません。
まず、親御さん自身に問い直していただきたいことがあるからです。
たとえば、ちょっと冷静に考えてみてください。
2〜3歳の子どもであれば、体格的にも力関係的にも、大人が“物理的に”どうにかすることは可能です。
- 保育園に連れて行く → 抱っこすれば行けます
- チャイルドシートに座らせる → 支えてベルトを締めれば乗せられます
それでも、「できない」と感じてしまうのはなぜか。
本当に困っているのは、
“どう行動すればいいか”ではなく、“どんな態度で接すればいいのか分からない”ということなんです。
泣き叫ぶ子どもを前にして――
- 「無理やりはかわいそうかな…?」
- 「怒るべき?でも怒りたくない…」
- 「この子に何て言えばよかったんだろう…」
そんなふうに、“親としてどうあるべきか”に迷ってしまう。
言い換えれば、子育ての“土台”がまだ定まっていない状態です。
この“土台”ができていないまま、
ひとつひとつの問題にハウツーだけで対応していると──
気づけば、「次々出てくる困りごとを、その場しのぎで叩き続ける」状態になります。
まるで「子育てのもぐらたたき」です。
なぜ親が揺さぶられてしまうのか?——難しくなる子育てへのヒント
2歳・3歳という時期は、
子どもが初めて「社会の壁」にぶつかりはじめる時期です。
たとえば──
- チャイルドシートに座るのは、安全のため。
→ でも子どもにとっては「窮屈でイヤ!」 - 保育園に行くのは、親が安心して働くため。
→ 子どもにとっては「置いていかないで…」 - 寝る前におやつはNG。虫歯を防ぐため。
→ 「ちょっとくらい食べてもいいでしょ!」
大人にとっては「当然のルール」も、
子どもにとっては「理不尽」と感じるものばかりです。
そして彼らは、「泣く」「叫ぶ」「暴れる」といった
赤ちゃん時代のレパートリーを、全力で繰り出してきます。
でも、ここで譲ってはいけないのです。
チャイルドシートは命を守るため
仕事には責任がある
虫歯は放っておけない
子どもには、「受け入れてもらうしかないルールがある」ということを、
少しずつ伝えていかなくてはいけません。
教育相談の中で、私が親御さんにお伝えするのは──
「ダメなものはダメ」という軸を持つことなんです。
伝え方や言い回しの工夫もあるのですが、それはどちらかと言えばテクニックの話。
でも、それ以上に大事なのは、
「ここは譲れない」という親としての姿勢を、落ち着いて示すことです。
- 「それは受け入れられません」
- 「ここはお父さん・お母さんのペースで行きます」
という態度を示す子育てです。
これがとにかくしんどい。世の中の親御さんの多くが苦手なことも分かっています。
大変で心が折れそうになります。
なので、2歳・3歳は、子育ての山場なんです。
お説教っぽい?——ここからが早期療育の腕の見せどころ
「正論ばかりで、なんだかお説教っぽい…」と思われた方も多いでしょう。
では、出張カウンセリングで一体何をするかというと…
お手本を見せます!
この一言に尽きます。
百聞は一見に如かずと言いますよね。言葉より見せてしまった方が早いです。
激しいかんしゃく、イヤイヤの拒否、パニックになるようなこだわり、歯磨きの方法——
出張カウンセリングでは、全ての対応方法を私がお見せします。録音・撮影だって大歓迎です。
一例となる記事を紹介しますね。
👉同じ質問ばかりの“こだわりパターン”――親にできる“こだわり崩し”とは?(後編)
👉「CMが怖い」って本気で?──3歳の“謎のこだわり”と向き合う支援とは
これらの記事。読んでいただくと、かなりの変化球を投げているように見えるかもしれません。でも実は――
- 「そんなこだわりに付き合えないよ」
- 「大人のペースも大事だよ」
と伝えるための、大切な練習なんです。
やっぱり、早期支援が大切です
イヤイヤも、かんしゃくも、
年齢が上がるほど対応が難しくなります。
いったん根づいてしまった習慣を変えるには、時間も根気も必要です。
だからこそ、“ちょっと気になるな”と思い始めた幼少期こそ、支援を開始すべきタイミングです。
最初に紹介したA君のケースでは、
いつのまにか「子どもが暴君」「親が召使い」という関係が出来上がっていました。
でも、あれは特別な話ではありません。
誰にでも、どの家庭にも、そうなってしまう可能性があるんです。
ですが、正しい支援につながれば、子育てはもっと楽になり、
何より、親子の毎日がちゃんと楽しくなります。
当相談室では、ご家庭に直接うかがって、その場で具体的な対応方法をお伝えしています。
「どうしたらいいか分からない」状態を、そのままにしないでください。
ご関心のある方は、こちらもご覧ください。
千葉県・東京都内近郊を中心に、療育支援の専門家が出張で支援しています。
出張カウンセリングのお問い合わせはこちらから。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。