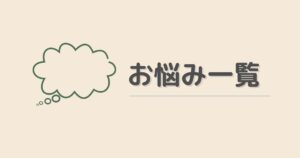ひとり寝と“強度行動障害”──家庭の未来を左右する理由
前編では、子どもの「ひとり寝」が親子に自立をもたらす理由をお伝えしました。
👉 子どもが一人で寝るのはいつから?“ひとり寝”の練習と親子の距離の考え方(前編)
この後編では一歩踏み込んで、“ひとり寝”が将来にどうつながるのかを考えます。
少し重たい話に感じるかもしれませんが、実際に相談の場面で親御さんに伝えている、とても大切なテーマです。
「強度行動障害」という言葉を聞き慣れない方も多いと思います。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
👉“今は困っていない”が一番こわい──強度行動障害という言葉、知っていますか?
強度行動障害の“芽”は日中だけじゃない──夜にも出るサインとは
教育相談で寄せられるケースの中には、すでに次のような行動が“日常化”していることがあります。
- 他人を叩く
- 自分を傷つける(自傷行為)
- 物を投げたり壊したりする
もし幼少期からこうした行動が繰り返されている場合、早期の対応が不可欠です。
早期支援が大切なことは、こちらの記事でもお伝えしています。
👉落ち着く力を育てる一人遊び──社会適応と強度行動障害予防のために(後編)
もちろん、背景には重度の知的障害や自閉スペクトラム症の特性が関係していることも多いでしょう。
ですがここでは、診断名にとらわれず、“行動の現れ方そのもの”に目を向けてほしいのです。
最初の相談では、どうしても昼間の困りごと(行動上の課題)ばかりが話題になりがちです。
でも私が、ふとこんなふうに尋ねると、別の問題が浮かび上がってきます。
夜も眠れていないんじゃないですか?
多くの親御さんが、戸惑いながらも、
静かにこう答えられます。
……実はそうなんです
その言葉に、親御さんの疲れや苦しみがにじみ出ています。
つまり行動上の問題は──
「日中」だけではなく、「夜間」にも現れる
ということなんです。
夜になると始まる“家庭の崩壊”──眠れない親子に起きていること
このようなご家庭では、夜間に次のような困りごとが日常的に起きています。
- 夜中に大声で叫ぶ、暴れる
- 親を叩く、物を投げる
- 興奮して家中を歩き回る
- 何時間も同じフレーズを繰り返す、大声で歌い続ける
こうした状態が毎晩のように続けば、家族全体の生活リズムはすぐに崩壊します。
親御さんは眠ることができず、疲労が蓄積する一方です。
なんとか子どもを落ち着かせようと、
- 夜中にテレビや動画を見せる
- 食べ物を与えて気を紛らわせる
といった対応が“常態化”してしまうご家庭も少なくありません。
中にはさらに、
近所迷惑になるので、深夜に車で何時間もドライブしました…
どうしようもなくて、誰もいない公園に連れて行きました…
と語る親御さんもいました。
これがどれほど大変なことか、想像に難くないでしょう。
ここまでくると、もはや──
「子どもの睡眠が少し乱れている」では済まされないのです。
家族全員が休めず、心身ともにすり減っていく毎日を送ることになります。
「夜に寝る」というあたりまえを、家庭に取り戻すために
前編の記事で私はこうお伝えしました。
「悠長なことを言っていられないケースもある」と。
ここまで読んでくださった方なら、
「なるほど、こういうことだったのか……」と感じていただけたかもしれません。
では、一体どうやって立て直していけばよいのでしょうか?
その第一歩が、前回からお伝えしている「ひとり寝」の習慣づくりです。
最初は多くの親御さんが、こう不安そうにおっしゃいます。
本当に、そんなことできるんでしょうか……?
でも私は、はっきりとお伝えします。
このままでは、ご家族がもちません。
今から、“夜に寝る生活”を、家族みんなで取り戻していきましょう。
夜は、大人も子どもも静かに眠る時間。
その「あたりまえ」の習慣を、本気で作り直す必要があるのです。
こうしたご家庭の支援は、教育相談のなかでも特に神経を使います。
- 家族全員の生活リズム
- 家の間取りや寝る場所の配置
- 家具の固定や安全対策
- 集合住宅なら近隣住民との関係づくり
時にはホームセンターに出向き、備品を整えるところから始めることもあります。
「そんなことまでやるんですか?」と驚かれるかもしれませんが、
それほどまでに“環境づくり”は重要なのです。
ひとつひとつを丁寧に整えていくことで、
親子が離れ、安心して夜を過ごせるようになります。
これこそが──
将来の行動障害の予防となります。
「ひとり寝」は、どの家庭にも通じる“ささやかな自立”の一歩
ここまでの内容は、将来の強度行動障害を、幼児期から予防するという視点からお伝えしてきました。
「子どもが一人で寝る習慣をつけることで、家族の安心と生活を守る」
──そんな現場の実感を共有したかったからです。
でもこれは決して“特別なご家庭”だけに向けた話ではありません。
実は、ごく普通の子育てにも、深く関わるテーマなのです。
「ひとり寝」の練習が、ある家庭では“最初の課題”になるかもしれませんし、
別の家庭では“もっと後のステップ”になるかもしれません。
でも、どの家庭にも共通するのは──
子育てのゴールが「子どもが親元を離れて生きていくこと」
という点です。
18歳か、20歳か、もう少し先かもしれません。
けれど、いつか必ずその日はやってきます。
だからこそ、思い浮かべてみてください。
- 「おやすみ」と言って、自分の部屋へ向かう子ども
- 「ひとりはいや! こわい!」と叫ぶ子ども
どちらが、自立という未来に近づいていると思えるでしょうか?
毎晩の「ひとり寝」は、親子にとってのささやかな“別れ”の練習です。
それは、やがて訪れる“巣立ちの日”への、静かな準備でもあるのです。
子どもが自立する日を、少しずつ準備していく。
その道のりは、どの家庭にも共通しています。
前編も改めて読んでみてください。


今回は、ひとりで寝るというテーマを取り上げましたが、寄せられる相談はお問い合わせは様々です。
他にはどんな相談を受けているのかな?と、思われた方は、こちらをどうぞ。
出張カウンセリングが実際どんな形で行われているのか、雰囲気が少し伝わったのではと思います。
千葉県・東京都エリアで専門家による出張相談を希望される方は、こちらからお問い合わせください。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。