名前を呼んでも反応しない子ども──その行動には理由があります
2歳の子どもなんですけど、名前を呼んでも振り向かないんです。
テレビやおやつには反応するのに、親の声はスルーされてしまいます。
そんなご相談をいただくことがあります。
この「呼んでも振り向かない」という悩みは、親御さんからよく届きます。
何か発達の問題があるのでしょうか──?
今回のテーマは、「名前を呼んでも反応しない」子どもの行動についてです。
実は、この行動について、このブログの別記事でも触れていますので、まず紹介します。
👉 「3歳なのに会話にならない…」──“言葉が出ているのに通じない”ときの支援の考え方
親が声をかけたら、即座にパッとふりむいて反応する。
こうした練習方法を親御さんにお伝えし、療育の初期段階から重点的に取り組んでいきます。
なぜなら、これは──
発語だけでなく、人とのやりとりの基本となる、『肝心・要(かなめ)の行動』だからです。
この「呼ばれたときに振り向く」という行動には、子どもの“社会性の土台”がぎゅっと詰まっています。
だからこそ、療育を始めたら、まず最初に始めましょうとお伝えし、練習を開始するわけです。
ところが、この“最初にやるべきこと”が、支援の現場で軽視されてしまうこともあります。
次のパートで掘り下げていきましょう。
個性でも性格でもなく「スキル」──振り向く力は、練習で伸びる
2歳・3歳で名前を呼んでも振り向かない──
そんな子どもの様子を前に、「個性ですよ」「性格ですね」と言う支援者が、残念ながら存在します。
でも、はっきり言います。これは個性や性格ではありません。
名前を呼ばれたら反応する。
これは、人と関わるうえで大切な行動です。
それに、せっかくお母さんが声をかけてくれたのにスルーされるなんて、ちょっと切ないですよね。
家庭も、幼稚園も、学校も、そして社会も──すべて“人と過ごす場所”です。
その中で、呼びかけに反応する力は、やりとりのスタート地点になります。
呼ばれても反応しない状態を放置していれば、いずれ集団生活に馴染みにくくなるのは明らかです。
これは「その子らしさ」なんかではなく、まだ獲得できていない“スキル”と捉えましょう。
もちろん、スキルであれば練習によって必ず上達します。
私の相談室には、知的に重たいお子さんや自閉スペクトラムの特性が強いお子さんもいます。
しかし、「呼ばれたら反応する」は、どのお子さんでも必ず獲得することができます。
「様子を見ましょう」とだけ言って終わる支援者がいたら、それは事実上の“放置”です。
そのまま3歳、4歳と過ぎていってしまえば、より深い困りごとにつながっていく可能性もあります。
課題を“個性”にすり替える前に、やれることはたくさんあります。
「呼んでも来ない」のに、「呼んでないときに寄ってくる」理由──“主導権のズレ”に気づくことから
まず何から始めるんですか?名前をたくさん呼ぶとか?
それをやると、ますます来なくなります。まず“主導権”の話をしましょう
主導権?
親が呼んでも反応しない──
確かにそう見えるかもしれません。でも、少し整理してみましょう。
「親が名前を呼んでも、来ない」だけじゃなくて、
「親が呼んでいないのに、(勝手に)来る」
というパターンはありませんか?たとえば──
- おやつを準備していると、呼んでもいないのに気づいたら足元にいる
- 夕方、火を使っていて忙しいのに、ベタっとまとわりついてくる
- トイレに行くために少し離れただけなのに、「ギャー」と言って追いかけてくる
──発達支援ではよく見る「あるある風景」です。
ここをもう少し掘り下げると、こうも言えます。
「親が構ってあげられない・手が離せないときなのに、子どもが来る」
まとめると、親が来てほしいときに子どもは来てくれない。
逆に、呼んでもいないし、むしろ来てほしくないときに限って、子どもがやって来る。
この、“ねじれてしまった関係”を、親子の主導権のズレと表現しています。
このような関係が続いていれば、「どう声をかければいいか」「どんなタイミングで言えばいいのか」分からなくなってしまうのも当然です。
だから支援ではまず、このねじれやズレに目を向けるところから始めます。
これ、心当たりありませんか?
もう、心当たりしかありません
「呼んでも振り向かない」を変えるには──親が主導権を取り戻す練習
呼んで振り向いてほしいのに、振り向かない。
呼んでいないし、むしろ親が忙しいときに限って来る。
そんな状況を、「主導権のズレ」と表現しました。
ズレているなら、本来の形に戻せば良いだけです。
子どもが持っていた主導権を、親御さん側に取り戻していきましょう。
出張カウンセリングで家庭を訪問すれば、
お子さんがどのように主導権を握っているかなんて、すぐに分かります。
そうと分かれば、早速、大人側に主導権を取り戻す練習を開始します。
具体例を1つ挙げると──
大人同士で大事な話をしているときは、あなたのお相手はできません♡
お父さんやお母さんにまとわりつかず、あちらで1人で遊んでいてね♪
こちらのタイミングで呼びますので、しばし1人でお過ごしください☆
これを相談の最中、まさにリビングで行います。
子どもに言葉で説得したり言い聞かせたりせず、親子で体験として学んでもらいます。
かなり具体的な方法について、こちらの記事でも紹介しています。
👉 「全部受け止めてあげれば大丈夫」は本当?ママに執着した2歳児の事例
これが練習?でもそんなことしたら…
はい、もちろん最初は泣いたり怒ったりします
でも、大人は絶対に怒りません。
まとわりつこうとするお子さんを安全な方法で何度も離すので、私は汗びっしょりになることもあります。
子どもがちょっかいを出してきても、親はコンクリートのように固まって、ピクリとも反応しない。
そして何事も起こっていないかのように、大人同士の会話を淡々と続ける。
親御さんが、内心ハラハラしていることは分かっています。
もちろん支援者がそこをきちんとサポートします。
そして、いよいよここからです。
子どもがようやくあきらめ、1人で遊び始めたタイミングを見計らって──
おいで!
と、大人が満面の笑みで声をかけます。
すると──
!
あれだけ呼んでも来なかった子が、嘘のように、まっすぐ飛んでくる。
信じられない…
という表情の親御さん。
一方支援者の私は、にこにこしながら──
私にとっては“いつものこと”なんですけどね。
と、そんなふうに思っています(汗だくですが)。
あれだけ名前を呼んでも来なかった子が、離れることを教えたら来るようになる。
これが親御さんに主導権を取り戻した瞬間です。
不思議に思われるかもしれません。
でもこれが「臨床あるある」なんです。
呼ばれたら笑顔で振り向く──“あたりまえ”をつくる子育てへ
「親に呼ばれたら、100%反応する」
これを教育相談の中だけで終わらせず、生活の中でも“あたりまえ”になるように練習していきます。
そのためのキーワードは、ここまで何度も登場している「主導権」です。
子育てや保育、幼児教育の現場で「大人が主導権を持ちましょう」なんて言うと、あまり受けが良くありません。
でも、「名前を呼ばれたら反応する」という、ごく基本的な行動ひとつをとっても、
親御さんが主導権をしっかり握っていないと、子育てはどんどん難しくなっていきます。
道を歩くとき、お店に入るとき、電車に乗るとき──
親が指示を出しても子どもが反応しない状態では、そもそも安全に過ごすことさえ難しくなります。
「呼んでも振り向かない」という悩みの裏には、
今回紹介した“主導権のズレ”が隠れていることが多いのです。
私の教育相談では、目の前の困りごとを解決するだけでなく、
「子育てをどう考えていくか」という土台や価値観そのものにもアプローチしていきます。
「主導権を取り戻す」は、子どもを叱って従わせることではありません。
むしろ逆です。
子どもが、安心して親の声を頼りにできる関係を育てていくということ。
呼ばれたら笑顔で振り向く。
そんな“あたりまえ”を一緒に練習していきましょう。
同じような悩みからスタートし、実際に変化が起きたご家庭の記録は、こちらから読むことができます。


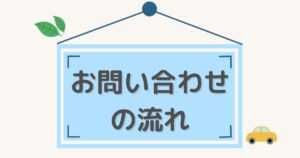
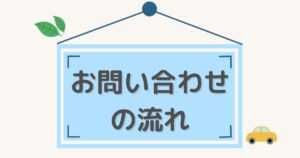
当相談室では、言葉や発達の遅れ、かんしゃくへの対応など、
子育ての悩みに出張カウンセリング支援します。
お問い合わせはこちらから。
- 対象年齢: ご相談時点で3歳未満のお子さま
- エリア: 千葉県・東京都を中心に出張対応
- 支援方法: 応用行動分析学(ABA)に基づいた支援プランを個別にご提案
- サポート内容: ご家庭での療育支援、親御さんへの具体的アドバイス
📩 お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。








